令和2年2月20日に東京・国立新美術館3階講堂で開催された文化庁主催シンポジウム。「企業の文化投資は経済界・文化界に何をもたらすのか」をテーマに、文化経済戦略推進事業の位置づけや戦略が説明され、また併せて文化芸術界関係者・企業経営者・アーティストといった様々な関係者が集い、世界の潮流や国内の事例を共有しながら、課題や今後の展望について議論した。
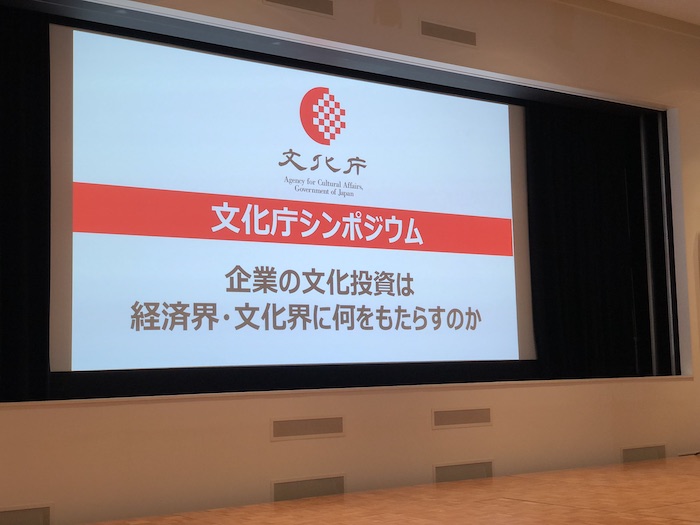
後編ではこれまでの登壇者に加えて、マツダ株式会社 常務執行役員の前田育男氏を交えてのパネルディスカッションの様子をお伝えする。

前田氏は、2010年に発表したデザインコンセプト「魂動(こどう)」を軸に、商品開発、展示会や販売店舗など、デザイン面を総合的にけん引してきた人物。パネルディスカッション前の挨拶では、CAR AS ARTを体現する事例として、2015年に発表された『Mazda RX-VISION(マツダ・アールエックス・ビジョン)』について解説された。
 余白・反り・移ろいといった「日本の美意識」や「異業種共創」、「手間をかける」といった、マツダのたゆまぬ挑戦と創造のプロセスについて語られた
余白・反り・移ろいといった「日本の美意識」や「異業種共創」、「手間をかける」といった、マツダのたゆまぬ挑戦と創造のプロセスについて語られた
<登壇者> ※左から順に

- 青柳正規氏(多摩美術大学理事長、山梨県立大学美術館館長、東京大学名誉教授、前文化庁長官) ※モデレーター
- 長谷川一英氏(株式会社E&K Associates代表)
- AKI INOMATA氏(美術家)
- 前田育男氏(マツダ株式会社 常務執行役員)
過去の整理と蓄積力が、アーティストのすごいところ

--アーティストの発想やアイデアって、一体どうやっているのでしょうか?
INOMATA氏:アイデアは割と雑談から生まれることが多くて、先ほどの(中編の)やどかり作品は、確かに旧フランス大使館のお話もあるのですが、それとは別のものとも交差して生まれた感じがあります。
複雑な社会状況を見ているだけでは一筋縄ではいかないので、他の要素も必要なのかなと思います。
長谷川氏:色々なアーティストの方とお話ししていると、その人が経験したことや勉強したことが、ご自身の頭の中にしっかりと整理して蓄積されていることをよく感じます。
例えば新しい展示物を創るときに、昔やったことと現在のことを結びつけて新しい物を創る、ということがよくあります。
私自身も蓄積が大事だと考えていますが、昔の自分がやったようなことはパッと出てこないので、そこがアーティストのすごいところだと、いつも思っています。
--以前イギリスの幼児教育レポートに、退屈がっている子どもほどクリエイティブ指数が高い、というものがありました。INOMATAさん、その辺りいかがでしょうか?
INOMATA氏:どうなんでしょう(笑)
退屈というのもありますが、「抑圧されていた」というのもあるかもしれません。これはダメと言われると、本当にそうなのかなとか思っていました。
あとは「欠乏感」もあると思います。よく「生き物が好きなんですか?」と聞かれまして、確かに好きなんですが、それはずっと都会に住んでいたからこそ、生き物についての興味が湧き出てくるんだと思います。
本当に必要なことは、本心に立ち返ること
--前田さんは会社でそういった活動を進めているわけですが、どうしても上手くいかない、という時はどうされているのでしょう?
前田氏:まあ、家に帰りますね(笑)もうそんなのしょっちゅうですよ。七転八倒の毎日です。
デザインの仕事なんて、なんとなくスタイリッシュなように思われますが、実際は汗だくで泥まみれの世界です。簡単にゴールが出てくるものに、人は感動しない。プロセスがすごく重要だし、物語も重要です。

--私自身、例えば伝統工芸だとかはもっともっと言葉化していかなきゃいけないと思っているのですが、やはり言葉も重要ですか?
前田氏:もちろん大事です。誰かの心を掴むことでお客様になるわけですから、作品に全精力注ぐのは当然として、それ以外のところにも精力を注がないと、海外には到底かないません。
車インダストリーではプレゼンテーションが非常に大事なので、訓練をしています。作品は一瞬が勝負。ハートを掴まなければなりません。
ただ本当に必要なのは、自分が根底から何を信じて、何を創りたいのかという“本心”に立ち返ることなんじゃないかと思います。
その心の中の叫びって絶対に伝わると思っていて、そこまで辿り着ければ、言っていることにも重みが出てくるし説得力も増すと思います。
--長谷川さん、この辺りを人材醸成として会社でシステム化することはできるものなんですかね?
長谷川氏:難しいところですね。システムというほどカチッとしたものは難しいと思いますが、自社に合わせる形でカスタム化して、アーティストの考え方をとり入れたイノベーションのやり方を作っていく必要があるとは思います。

--私、専門が美術の歴史なのですが、芸術家たちって意外に、本当のことも言うけど、そうじゃないことも言うんです。アーティストの言葉ってかなり注意して聞かなきゃいけないと思うのですが、INOMATAさん、その辺りいかがでしょうか?
INOMATA氏:アーティストはウソつきだってよく言われます(笑)
よく「コロコロ変わっている」と言われまして、確かにコロコロも変わっているのですが、それって「そうとも捉えられるし、こうとも捉えられる」と言う感じで、“どちらも本当”なんですよ。
さっき「正解が一つじゃない」とお話ししましたが、そこがアートの面白いところで、創っている本人としても実はコンセプトは一つじゃないし、AともBともCとも言えるけど全部本当なんです、と言うことがあります。
なので、そういうところを面白がってもらえるといいなと思っています。
正解を求めにいかないチャレンジこそが、新たな伸び代

--いま、色々なイノベーションが全体的に必要な状況なわけですが、一般的に考えると、イノベーションは一種のトランポリンなわけです。だから、トランポリンのバネが張っている時はそこでジャンプをすれば高く跳べます。でも、今みたいにあまり経済状況が良くないと、バネは弛緩しているので、高く跳ぼうと思っても難しい。そこで、文化芸術や福祉、環境といった経済以外の要素を入れると、もう一度張りが出てきて跳べるようになるんじゃないかと思っているのですが、その辺りはいかがお考えでしょうか。
長谷川氏:いまテクノロジーが発達している中で、ユーザーは完全に“満足”してしまっています。だから、次に何を創ればいいかが相当難しくなっている時代だと思っています。
だからこそ先生がおっしゃるように、環境や文化などの別の観点で課題を見出して、そちらを解決する。そのような方法に向かっていくことが、先ほど(中編で)申し上げた「意味のイノベーション」につながっていくと考えています。
前田氏:いまトランポリンのバネがシュリンクしているのは間違いないですし、正解を求めようとすると跳べません。
一方で、例えば「車とアート」を考えると、本来はご法度の関係。車はアートになり得ないというのが一般常識です。車の「利便性」などをバネにみんなが跳ぼうとしているときに、私たちは全然違う方向のバネを装着して、そこで跳ぶ。
このような「正解を求めにいかないチャレンジ」というのが、新たな伸び代・跳び代を作れるのではと思っています。

--私、前田さんがデザインした車が大変好きでして。真っ赤なRXなんか、ちょっとした角度で色が変わるんですよね。あれだけアーティスティックな車は他にないですよね。
前田氏:芸術作品というのは本当におこがましくて声が震えますが、一般的な車の作り方をする限りは絶対にたどり着かないところなので、例えば色も、相当違った発想から創っています。
あれって、実は“赤”じゃないんです。黒の上にシルバーを塗って、その上に赤いクリアのコートを吹いているんです。いかに形に反応する色を創るかを研究するために、実は塗装メーカーというよりかは金属メーカーと一緒に考えていきました。
現代科学をもって、古典のアートを実現する。そういう感じです。
過去のノウハウと今の科学やテクノロジーを使うことで、現代で確固とした価値を産めるのではないかと思っています。
やっていないことへの突破のカギは「協働制作」にあり
--現代アートって、人がやっていないことをどうやるかだと思うのですが、やってないことを見つけるのって難しくないですか?
INOMATA氏:やり尽くされたんじゃないかと思うことはよくありますね。こんなことをやってみようかな、はだいたいやられています。
私の場合は、そこを突破していく方法を「協働制作」に見出しています。誰かと一緒にやったものを、さらに次のステップへとどんどん進めていくと、そこでやっていないことへとたどり着けると考えています。その連鎖反応が楽しみですね。

--そういう観点で、先ほど(中編で)ご紹介いただいた現美新幹線はいかがでしたか?
INOMATA氏:あれ自体、例えば一人でやろうと考えても絶対できないし、私の方から持ちかけたとしても、なかなか実現しなかっただろうと思います。
新幹線ってたくさんのレギュレーションがある中で、あのような企画が実現できたのは、非常に貴重なことだったと思います。
あと、移動しながら作品を観るってなんだろう、という新しい問いも出てきました。
--長谷川さんご自身も、お薬をやっていたりアートをやっていたりと、多くの異分野を体験されています。こういう組み合わせだとこういう面白いことが起きる、というご経験はいかがでしょうか。
長谷川氏:いま実は大学の広報を少しやっているのですが、そこでの取り組みは面白いです。
地震がきた時に、建築家は建物が壊れないように研究をしているわけですが、中でも高層建築の上層階って、一度揺れ出すとずっと揺れ続けます。故に、そこの住人の方々は、いつまで揺れるのかと不安になるわけです。
そこで今、建築家と心理学者が共同で、長く揺れているときにどういう情報を出せば住人の不安を軽減させることができるか、という研究を進めています。
ハードを強固にするだけでなく、ソフト面からも安全・安心を担保するという取り組みでして、異分野として面白い取り組みだなと感じています。
日本固有の文化に目を向ける、ベクトルのイノベーションを起こせ

--最後に改めて、今のVUCA時代において、どのようにイノベーションを起こせば良いか、それぞれの考えをお聞かせください。
長谷川氏:私としては異分野のコラボレーション、特にアーティストとのコラボが一つの解になるんじゃないかと考えています。
とはいえ、アートと企業がどうやって出会えばいいのか、という悩みを持っている会社も多いと思いますので、その辺りのマッチングについて、文化庁さん含めて一緒に進めていく必要があると思います。
INOMATA氏:アーティストって個人戦に見えるかもしれませんが、実はそうでもなくて、一人で戦うと弱いので、仲間を増やしていくことが大切だと思います。
チーム戦で戦っていくことに、私は可能性を感じています。
前田氏:最近イノベーションという言葉が乱用されていると感じており、イノベートすること自体が目的になっていることが多くなっています。何のためにイノベーションが必要なのか、ということをもう一度考え直すべきでしょう。
日本は美術や技術など、色々なものを固有の文化として持っています。だからこそ、そこに目を向けてツールとして伸ばしていくという、ベクトルのイノベーションなるものを起こせば、まだ色々なチャンスに溢れていると思っております。
編集後記
芸術作品の鑑賞の仕方って確実に変化していて、例えば今まで触れなかった工芸品や絵画などをVRで再現して、中身をのぞいたり解剖したりする試みが、各所で行われています。
先日当メディアで報じた以下のニュースも、日本工芸の名宝に対する新しい鑑賞アプローチの提案という意味で、とても意義があると感じました。
[clink url=”https://lovetech-media.com/news/family/20191214_01/”]
では、これまでではなく「これから」の作品づくりを考えるとどうなのかというと、やはりキーワードは「コラボレーション」「協働」なのでしょう。
アートは「ちがい」を楽しむもの。
これまでの均一化・標準化による「正解を求めるアタマ」ではなく、STEAM学習などを通じた「ちがいを楽しめるココロ」の醸成が、ますます求められる時代だなと感じるセッションでした。














