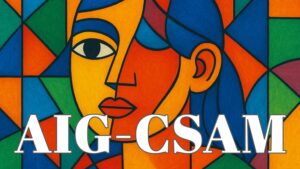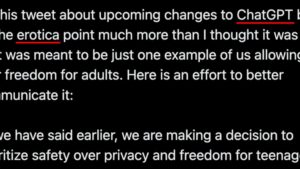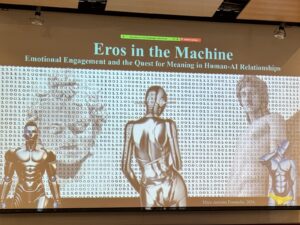人類の歴史=身体性拡張の歴史
「AI時代に人間は何をすれば良いのか?」
そんな質問に一辺倒の正解なんてあるわけがないのだが、メディアはこぞって来るべき未来像を予想し、時には各専門家の知見を総動員して、中長期的に必要となるであろう(と想像する)社会リテラシーを啓発している。一方で現実社会に目を向けてみると、実際のところ例えば新型コロナの到来なんて誰も予想できなかったわけで、結局は誰も未来を正確に読むことなんてできないのは、わかりきったことである。
そんな身もフタもない前提ではあるものの、LoveTech Mediaもまた、これからの時代にあるべき“未来リテラシー”について考えることはある。その一つが、人々がもつ「身体性」の拡張だ。ここでいう身体性とは、我々の奥底に眠る「真善美」なる感覚をエンパワーする身体の働きとも言えるもので、各身体パーツによる機能性の総体以上の“何か”をもたらしてくれるものである。ここでいう“何か”が実際になんなのかは未だ解明されていないが、少なくとも常日頃から所与の条件となっている身体感覚の前提条件が変わった際に、人々は一種のセレンディピティと共に、受け取る感覚も多様化するに違いない。
そもそも以下の記事でも言及されている通り、人類の歴史とはすなわち、道具を駆使してきた歴史とも言い換えられ、もっと言えば「身体性拡張の歴史」とも言える。
[clink url=”https://lovetech-media.com/interview/20190226caretechforum/”]道具は、当初は自立共生のためにあるべきものだったが、近代以降は身体と意識を分断することで、いつの間にか“Modernized Poverty”(近代化された貧困)なる状態をもたらしていった。ここ最近における、改めての「身体性の拡張」論は、このModernized Povertyへの反動とも受けとれるだろう。
この身体性の拡張については様々な手法があるが、我々の日常生活において最も身近なアプローチの一つが「ファッション」のアップデートにある。いや、アップデートというよりかは、意味のイノベーションを前提にした“ルネッサンス”に近いかもしれない(「意味のイノベーション」についてはこちらの記事を要参照)。
本記事では、フットウェア(シューズ)の世界において、「重力との関係性」を再定義して身体性の拡張を進めているファッションテックブランド「grounds(グラウンズ)」について、その思想や目指す世界観等について伺った。
 2020年6月27日〜7月5日の約一週間で限定オープンしている「grounds」ポップアップストア@GALLERY202
2020年6月27日〜7月5日の約一週間で限定オープンしている「grounds」ポップアップストア@GALLERY202
はじめにセレンディピティあり
最初に当メディアがgroundsに触れたのは、昨年度のTechCrunch Tokyo 2019 Startup Battle取材中であった。
[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191116tcstartupbattle/”]
と言っても、groundsチームがスタートアップバトルに出場したわけではない。審査員として登壇されたエンジェル投資家・赤坂優氏が、goundsブランドである「ジュエリー(JEWELRY)」タイプのシューズを着用していたのだ。
 エンジェル投資家 / 株式会社エウレカ共同創業者 赤坂優氏(2019年11月15日 TechCrunch Tokyo 2019 Startup Battle ファイナルラウンドにて)
エンジェル投資家 / 株式会社エウレカ共同創業者 赤坂優氏(2019年11月15日 TechCrunch Tokyo 2019 Startup Battle ファイナルラウンドにて)
まさにセレンディピティ。一目見て、これまでのフットウェアブランドにはない「ファッション性」と「物語性」を感じたのが、groundsを認知したきっかけである。
JEWELRY, INTERSTELLAR, and VORTEX
groundsブランドには大きく分けて3タイプのシリーズ、「ジュエリー(JEWELRY)」「インターステラー(INTERSTELLAR)」、そして新作となる「ボーテックス(VORTEX)」がある。
まさに宝石のようなJEWELRY
まずは、赤坂氏が履いていたこちら「ジュエリー(JEWELRY)」タイプ。「履く宝石(ジュエリー)」というコンセプトで設計されたものだ。

ソール部分が、まるで立体的な戦車のキャタピラーのように個性的な作りとなっており、一歩ずつ踏み込む度に地面に“吸着”するような歩行体験を提供している。見た目はゴツい印象だが、ソールは柔らかい素材でできているので、地面の形状に沿って柔軟に曲げることができる。
この投稿をInstagramで見る
リリース直後はモノトーン4色のみの展開だったが、現在は以下の通り、23色(2020.6.28時点)ものバリエーションが投入されている。
 画像出典:grounds公式オンラインストア
画像出典:grounds公式オンラインストア
重力を忘れさせてくれるINTERSTELLAR
次にこちらが「インターステラー(INTERSTELLAR)」タイプ。

自然と足が前に進む流線型のアウトソールは、どこまでも歩いていけるような気分にさせる履き心地。まるで地球の重力を忘れさせてくれるような“軽やかさ”を意識したモデルとなっている。
この投稿をInstagramで見る
こちらも、リリース直後はモノトーン4色のみだったが、現在は16色(2020.6.28時点)のカラーを展開。よりストリートに寄せた形のラインナップを、意識的に揃えているという。
 画像出典:grounds公式オンラインストア
画像出典:grounds公式オンラインストア
浮遊感を醸し出すVORTEX
最後に、こちらが「ボーテックス(VORTEX)」タイプ。今年6月24日に発表されたばかりの新作モデルである。

月を半分にカットしたような丸みのあるクリアソールは、一見シンプルに見えるが、地面とアウトソールの接点を極限まで削ぎ落とし、地面との接地面が見えないデザインになっている。また、ソールの材料を可能な限り柔らかくすることで、見た目だけでなく、感覚的にも浮いているような錯覚をおこす仕様となっている。
この投稿をInstagramで見る
記事執筆時点で、リリースされてまだ4日しか経っていないが、早くもオンラインストアの在庫は全色全サイズ“SOLD OUT”となっていた。
 画像出典:grounds公式オンラインストア
画像出典:grounds公式オンラインストア
うちのブランドで決めているのは、機能性を捨てること。
このgroundsシリーズを手がけるのが、2019年3月設立されたばかりのスタートアップ、株式会社FOOLSだ。「ファッションブランドのあり方を未来へと前進させる」というミッションを掲げる同社には、ファッションデザイナーの坂部三樹郎氏が参画。過去には2019s/sパリコレクションに参加しており、2019年8月には総額3,100万円の第三者割当増資を実施した。先述の赤坂氏はgroundsのファンであると同時に、投資家のお一人でもあるというわけだ。
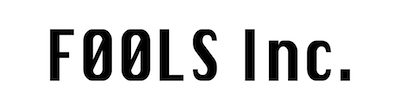 まだ何者でもなく、何者にもなれる可能性がある「未完成で危なげだが意志と希望を持ったチーム」という意味を込めた社名となっている
まだ何者でもなく、何者にもなれる可能性がある「未完成で危なげだが意志と希望を持ったチーム」という意味を込めた社名となっている
「うちのブランドで決めているのは、機能性を捨てるということです。」
こう話すのは、同社代表の金丸拓矢(かねまる たくや)氏。金丸氏は前職での3Dプリンターを使ったプロダクト事業を経て、未経験となるフットウェアブランドを起業することになったという。
 株式会社FOOLS 代表取締役 金丸拓矢氏(with VORTEX)
株式会社FOOLS 代表取締役 金丸拓矢氏(with VORTEX)
金丸氏:「スニーカーって、ほとんどのブランドは“スポーツ”でブランディングしています。つまり、身体性をサポートするための“機能”に軸を置いているのですが、実はそれ以外でブランディングをしているところは、ほとんどないんです。」
靴市場を俯瞰してみてみると、日本市場だけを見ればほぼ横ばいだが、例えば米国では年々市場規模が拡大しており、近年特に注目されているリセール市場を中心に650億ドルを超えるとも言われている。またファッション業界の観点から見ても、世界的なハイブランドが続々とスニーカー領域に進出するという潮流があり、市場としては上昇トレンドであると言える。だからこそ、「靴の選択肢が圧倒的に少ないことが課題だ」と金丸氏は続ける。

金丸氏:「例えばスーツを考えてみると、あれは人の顔を中心に設計されているわけです。ほとんどのファッションは、顔起点なんですね。
じゃあ靴から人間を設計したらどうなるのか、というデザインへの挑戦が、現在のgroundsのきっかけでした。
さらに、アッパーだけオシャレにしても他のファッションブランドとやってることが変わらないよね、どうせだったらちゃんとソールからやらないとダメだよね、との発想から、grounds特有のソール形状が生まれていきました。歩くという体験のデザインは、ソールしかできませんからね。
機能性ではなく、どういう体験をしてもらうか。身体性の“サポート”ではなく、身体性の“拡張”という観点で、日々の作品をマッピングしています。」
アッパーはむしろレトロな、80年代のようなデザインに

一般的な靴屋をイメージしてもらうとわかると思うが、私たちがシューズを選ぶとき、ほとんどの方はアッパーデザインの好みを第一の判断基準にしているのではないだろうか。だからこそ、多くの靴は店頭に並んだ際の「目立ち方」にデザインの軸が置かれており、存在感のあるロゴが中心部に据えられている印象だ。
一方でgroundsの戦略は真逆だという。
金丸氏:「groundsは、どれだけ情報量を少なくできるかという点で設計をしています。だからロゴも表に出さず、素材もニットを使っています。
ソールが未来感のあるデザインだからこそ、アッパーはむしろレトロな、80年代のようなデザインを心がけています。」
この「過去と未来」という時間軸のコンセプトは、「物事はいずれ、風化して砂になる」というコンセプトをベースに、2020ssシーズンのSAND(砂)コレクションのデザインとして表出させている。
 2020 s/sシーズン『サンドコレクション』
2020 s/sシーズン『サンドコレクション』
金丸氏:「リリースから1年が経過して、顧客層が広がっていく中でバリエーションを増やすことも大事なので、最近ではニット素材の他に、テキスタイルやレザーを使ったものも作っています。
とはいえ、やはりgroundsのルーツであるニットは根強く人気がありますね。」
3Dプリント × D2Cで、サステナブルな事業体制を構築
さらにLoveTechポイントとして明記したいのは、シューズの生産および流通過程において、より持続可能性(サステナビリティ)を追求している点だ。具体的には、3Dプリント技術を使った研究開発を進め、またD2Cをメインとした受注生産システムを構築することで、在庫処分を限りなくゼロに近づける工夫を続けているという。ちなみに「D2Cをメインとした」と記載したのは、groundsは「atmos Shinjuku」や「ROYAL FLASH Ueno」など、複数の実店舗での販売も行われているからだ。

金丸氏:「D2Cについては、今は公式オンラインストアの他に、インスタグラムによる非言語コミュニケーションがメインの販路となっています。言語的な部分は、今回のようなポップアップストアなどで補っていますが、今後はストーリーを明文化するなどして“言語化作業”にも注力していく予定です。」
また、サステナブルなブランド戦略の一環として、今年5月よりスタートした取り組みが、「FREE FIT PROMOTION」施策である。これは、無料で自宅試着できる仕組みであり、返品文化が欧米ほど普及していない日本において、返品交換無料ではなく、購入する気持ちが弱くてもまず履いてみたいという顧客に向けて、試着自体をプロモーションにする取り組みだ。

試着用の靴は、製造や物流上のトラブルや、外での撮影などが原因で傷や汚れがあり、販売ができないアイテムを利用している。
金丸氏:「もともとコロナ以前より企画しており、本当はもう少し在庫ロス分が溜まってからの展開を予定していましたが、新型コロナをきっかけに、予定を前倒ししてスタートすることにしました。」
《FREE FIT PROMOTIONの流れ》
- 申し込み:「グラウンズ」公式オンラインストアより、試着のお申し込み(1,000円+税を預かり、靴が返品され次第返金する。2サイズ各1足選択可能、色の選択は不可)
- 試着:試着品が届いたら、自宅、もしくは外での試着も可能(雨天時の利用はNG)
- 返送:到着時と同じように梱包し、同梱の着払い伝票で集荷依頼(到着から1週間以内に返送)
- 返金:試着品が返送され次第、1,000円+税の預かり金を返金処理
フットブランド→総合ファッションブランドへ

金丸氏:「やり始めて感じたことですが、スニーカーは本当に、参入障壁がめちゃくちゃ高いです。基本的に、まず工場といった、靴を物理的に作れるところへのアクセスが難しい。また、一個目の型を作るのに数百万単位でお金が必要になります。
一方で、3Dプリンターで作るという方法もありますが、これだと今度は量産のコストがかかってしまう。一個作るのに8時間近くかかってしまうのが現状です。」
業界未経験の立場だからこそ、ファーストステップは非常にハードルの高いものとなったが、地道なブランド戦略が奏功し、創業から一年強で早くも根強いファンの獲得に成功。JEWELRYに至っては、試着からの購入率が80%を超える店舗もあるという。
金丸氏:「私たちが目指すのは、総合的なファッションブランドです。
現在は靴下や靴紐といった周辺の部分のみ扱っていますが、中長期的にはアパレルなど、徐々に裾野を広げていく予定です。」

今回お邪魔したポップアップストアは2020年7月5日まで。新作「ボーテックス(VORTEX)」の先着60名限定での予約販売の他、新色「ジュエリー トリプルブルー(JEWELRY X3 BLUE)」の販売、ジュエリー(JEWELRY)シリーズの22cm・23cm(一部)含む2020s/sシーズンアイテムの販売、過去シーズンアイテムのサンプル販売と、grounds未開拓者にとってはまたとないチャンスとなっている。

「重力との心地よい関係」を体験してみたいと感じた方は、ぜひ足を運んでみてはいかがだろう。善は急げだ。
《ポップアップストア概要》
期間:6月27日(土) 〜 7月5日(日)
時間:12:00 – 20:00
場所:GALLERY202 東京都渋谷区神宮前5-17-24 CAT STREET BUILDING 2F(カンナビス隣)
編集後記
ファッションに頓着がない私にとって、スニーカーなんて履ければ十分という意識だったわけですが、今回のgroundsは超例外的にファンになってしまいました。
一回履いてみるとわかるのですが、例えば私の購入したINTERSTELLARの場合は特に「目線」が高くなり、これまで見えていた世界そのものに変化をもたらしました。
「それだったら、厚底ブーツを履けばいいじゃん」
そう思われるでしょうが、第二のポイントは「歩行時の独特のフィット感」にあります。INTERSTELLARは、靴先に向かうにつれてソールが反り上がっているので、歩くときに抵抗なくグイグイと進む感覚になります。一般的な厚底ブーツとは、足による移動という人間工学的観点が全く異なると感じます。
また、ポップアップストアでJEWELRYやVORTEXも体験してみましたが、前者についてはまるで「芋虫」のようなグリップ感が、後者については氷上を滑るような浮遊感を、それぞれ感じました。
1990年代〜2000年代初頭にかけて活躍した米プロレスラー・Scotty Ⅱ Hottyのフィニッシュ・ムーブに「The WORM」というパフォーマンス系必殺技があるのですが、JEWELRYの歩行感は、The WORMの視覚情報から感じる独特の前進感を通常の歩行に集約したような、まさにワームのような感覚をもたらしてくれます。
拡張された身体性は、世界に対する新たな風穴を与える。
そんなアハ体験をもたらしてくれるgroundsは、間違いなく、スニーカー界におけるルネッサンスの旗手だと感じます。
 筆者が購入したINTERSTELLAR GRAY / CLEAR
筆者が購入したINTERSTELLAR GRAY / CLEAR