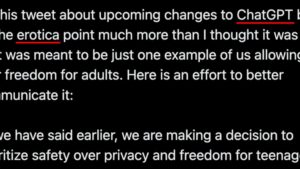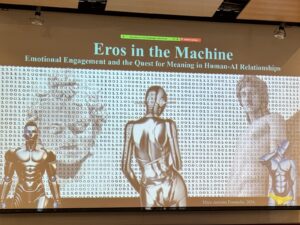※本記事では、作品の核心に迫るネタバレは含みませんが、何点かの劇中シーンについて解説がなされます。
2019年12月20日、東京・表参道にある脚本スクール「シナリオ・センター」にて公開講座が開かれた。テーマは映画『カツベン!』(※1)。ちょうど一週間前となる12月13日に劇場公開された、周防正行(すお まさゆき)監督の最新作である。
登壇ゲストは、周防監督と、本作の監督補であり脚本を執筆された片島章三(かたしま しょうぞう)氏。周防監督にとって、ご自身以外が書かれた脚本でメガホンをとるのは初めてだという。
 写真左:片島章三氏、写真中央:周防正行監督、写真右:柏田道夫氏(モデレーター)
写真左:片島章三氏、写真中央:周防正行監督、写真右:柏田道夫氏(モデレーター)
(写真提供:シナリオ・センター)
当日は超満員となる会場の中、脚本家である柏田道夫(かしわだ みちお)氏モデレーションのもと、作品成立の背景や過程はもとより、自作でない脚本作品を撮ることで初めて気づかれたシナリオの面白さなど、計1時間半に渡ってお二人の想いが語られた。
 超満員状態の会場(写真提供:シナリオ・センター)
超満員状態の会場(写真提供:シナリオ・センター)
これまで愛に寄り添うテクノロジー(技術)という観点で、主にテックプロダクトを中心に取り上げてきたLoveTech Mediaだが、テクノロジーは何も“科学技術”の専売特許ではない。むしろ、メディア名に“Tech”を冠しているからこそ、その解釈を拡張し読者のミソ帳(※2)の幅を広げることが、当メディアの一つの役割だと考えている。
今回は『カツベン!』という作品の解説を通して、日本映画黎明期における撮影技術等を学ぶとともに、映画作品の設計図でありひいては全てのストーリーテリングの叡智が詰まった「脚本」技術の一端を紹介すべく、本イベントレポートをお送りする。
※1:「カツベン」とは「活動弁士(かつどうべんし)」のこと。まだ映画というものに音が入る前の、いわゆる無声映画(サイレント映画)が上映されていた時代に、スクリーンの傍らでその作品内容を解説する“専任の解説者”のことである
※2:ネタノートのこと。ちなみに本イベントは、シナリオ・センターによるイベントシリーズ『Theミソ帳倶楽部』の一環である
僕自身、若い頃から活動弁士を全く無視していた
 (写真提供:シナリオ・センター)
(写真提供:シナリオ・センター)
--「カツベン!」の構想はいつ頃から持たれていたのでしょうか?
片島氏:そもそも興味持ったのは、20年くらい前になります。
もともと僕は映画少年ってわけではなかったのですが、中学1年の時に劇場でチャップリンのリバイバル上映を観まして、その時「ああ、映画って面白いんだな」って実感して。それで無声映画に興味を持つようになったんです。
そんな中、たまたま見たテレビの情報コーナーで活動弁士のことを紹介していました。「活動弁士というのは監督や役者よりも花形で、当時の大スターだった。台本はそれぞれの弁士が独自に作っていたので、同じ映画でも弁士によって内容が変わったりする。その弁士の語りにお客が付き、贔屓(ひいき)の弁士目当てに劇場に足を運んだ。」そんな話を知って、興味を持つようになりました。
そこから実際に、澤登翠(さわと みどり)さんという現在関東で第一人者の活弁を観に行きまして、まるで3D映像を見ているように映画が立体的に入ってくる感覚がして、本当に感銘を受けたんです。
その時に、いつかは活動弁士について書きたいと思いました。
--実際に取材も進められていたんですか?
片島氏:本格的に取材しだしたのが、監督が決まって実際に動きだしてからですね。それまでは図書館に通って、コツコツと調べながらホンを書いていました。
監督に初めてホンを見せたのは、『舞妓はレディ』(周防正行監督作品、2014年公開)が終わった頃だったと思います。
--監督の感想はいかがでしたか?
周防監督:面白かったです!絶対に映画にした方が良い、と話しました。その時は、自分が撮るとは思っていませんでしたが。
まず、脚本から「活動弁士たちの物語を描きながら、その物語自体をまるで活動写真のように撮りたい」という狙いが伝わってきました。すごく良いアイデアだと思いましたね。
あとは、活動弁士という存在を多くの人に知ってもらうという点も、もちろん面白かったです。
というのも僕自身、若い頃から活動弁士を全く無視していたんですよ。昔から無声映画はかなり見ていて、ずっと無音状態で見ていたんです。実際に、例えば小津安二郎監督の無声映画を見ると、「音いらないじゃん」と思いましたからね。なので、活動弁士という存在を知ってはいたものの、僕の中では「関係ないもの、余計なもの」だったんです。
でも片島さんのシナリオを読んで、あの時代、世界中で本当に無音で観ていた人なんていないじゃん、ってなったわけです。当時の映画監督も、これはサイレントで観られるもんじゃない、という前提だった。
そうなると、これまでの僕の無声映画の見方って、実は邪道だったんだな、と思ったんです。
 (写真提供:シナリオ・センター)
(写真提供:シナリオ・センター)
--活動弁士って、日本独特のもので、当時は8,000人近くいたと言います。なんで日本だけで発達したんでしょうね?
片島氏:想像の範囲ですが、日本独自の話芸の存在があったからかなとは思います。人形浄瑠璃とか落語とか。
周防監督:人形浄瑠璃だけじゃなくて、江戸時代から写し絵という影絵劇に語りのついた娯楽が親しまれていたり、昭和初期から子どもたちに人気のあった紙芝居のように絵に語りをつけて見せたりと、活弁というスタイルがことさら特別なものではなかったんですよ。そこに無言で動く写真があったから、説明してみました、ということ。
日本で最初に映画が上映されたその日から、当たり前のように人が立って説明していたわけです。
昔の無声映画がどうやって作られていたか見せたかった
 (写真提供:シナリオ・センター)
(写真提供:シナリオ・センター)
--『カツベン!』には様々な無声映画が出てきますが、あれらはどうやって作られていったのですか?
片島氏:手元にあった映像資料や、活弁付きの無声映画上映会を監督と一緒に見に行ったりしながら、オリジナルで作っていきました。冒頭のシーンで出てくるのは、“目玉のまっちゃん”(二代目 尾上松之助)の『怪猫伝』と『後藤市之丞』ですね。
目玉のまっちゃんの映画ってほとんど残っていなくて、主演作が千本以上あると言われていますが、ちゃんと残ってるのは数本で、それも完全版ではないんです。
『怪猫伝』のもとになった作品は当時のスチールが1枚あるだけの『怪鼠伝』。
『後藤市之丞』に至っては、『後藤半四郎』という実在の作品タイトルだけから、なんとなく想像して作っていきました。
--なるほど。
片島氏:そもそも今回、昔の無声映画がどうやって作られていたか、というのも見せたかったんです。知識がない中で非常に参考になったのが、監督が持ってきた映像資料でした。40年くらい前のテレビ番組で、『あゝにっぽん活動大写真』(※1)というものです。
映画監督のマキノ雅弘さんという、牧野省三さんの息子さんによる話を元に作られた再現ドラマでして、その中で、牧野省三が撮影中にどうやって立ち回っていたかも再現していました。撮影中に“まっちゃん”が台詞の代わりに「いろはにほへと」と喋っていたり(※2)、今だったら「よーい、スタート!」のところを「おいっち、にのにのにのさん!」と言ったりしていたんです。
※1:映画監督マキノ雅弘の著作「映画渡世」を素材に、大正、昭和の知られざる映画史、スター誕生の裏話をミニドラマと関係者の証言取材を交えて紹介するドキュメンタリーショー(Webサイト「テレビドラマデータベース」より引用)。1978年1月1日から同年3月26日までTBS系列局にて放送。制作プロダクションはテレビマンユニオン。
※2:無声映画なので撮影時の音声が入ることはなく、故にケースバイケースで台詞が「いろはにほへと」や「ちりぬるを」と言った言葉で代替されていた様子が、映画『カツベン!』でも描かれている
周防監督:マキノ雅弘さんの『映画渡世・天の巻』『地の巻』という本があって、そこに牧野さんの映画人生が全て語られているのですが、「いろはにほへと」はその中で紹介されている、牧野省三さんの有名なエピソードです。もちろん当初は舞台作品の映画化でしたからセリフの入っている役者もいましたが、例えば子役がまだ台詞を覚えられない時に「いろはにほへと、言うとけ」と指導したわけです。
1日1本くらいのペースで撮り、定番の芝居の映画化ではなく新作劇だったから、皆に配られる脚本もなかったようですから、覚えられるわけがないですよね。口さえ動いていれば、あとは活動弁士がセリフをつけてくれる。
--作品では他にも、本番撮影をずっと長回しする描写も描かれていますよね。
周防監督:当時は、カットして後から編集するという発想がまるっきりないんですよ。途中でアクシデントが起きても、やり直すということもなく、そのまま長回し。だから片島さんのホンにもある通り、例えば本番撮影中に犬が入ってきても、止める術がなく、そのまま撮影するしかなかった。
今でこそ、僕らは当たり前のように映像を見ていますが、写真が動くということが、当時の人にとってはどれだけの驚きであったことか。そういう時代だったわけです。
『あゝにっぽん活動大写真』の中のエピソードにもありますが、牧野省三さんが本番撮影中に、フィルムがなくなったのでフィルムチェンジをするんですが、カットを割る技術がなかったから、全員がストップモーションよろしく姿勢を変えずに新しいフィルムが装填されるのを待っていたんですね。また同じところから動き出せば、画がつながるからです。ところがひとりの演者がトイレに行ってしまった。でも牧野さんは気づかずに、その演者が戻って来る前に撮影を再開しちゃった。
それで撮ったフィルムをつないだら、その演者が「消えた!」っとなったんです。
でも、そこで失敗だったと落ち込むんじゃなくて、「こうすれば人が消える!」という発見につながったんです。逆に言うと、途中から人が入ると、突然現れることになる。そこから、忍者映画を撮っていくことに繋がっていったんですよね。
人間の目って、全部ひと繋がりでしか世界を見ていないので、違うアングルや違うサイズで撮影した一つひとつのカットを一連の動きとして編集するなんて中々思いつかないんですよ。だから、失敗を通じて発見したことが、新たな撮影手法につながることも多かった。面白いですよね。
人のホンだと、追いつくのが大変
 (写真提供:シナリオ・センター)
(写真提供:シナリオ・センター)
--周防さんにとって、人の脚本での監督は初めてだったわけですが、いかがでしたか?
周防監督:楽! すごく楽でした。やはり、自分で書くほうが大変です。
一方で難しい点もありました。
シナリオを書く時って、何を捨てたか、と言うことを自分で知っているんですよ。このシーンへと自分がたどり着くまでに、何を考えて、どういう理由でそれを残したのか、を分かっている。要するに、ホンには書かれていないことが沢山あるんです。
監督だけやるってことは、それを知らないで撮るってことなので、脚本家の狙いを理解するのが大変なんです。
なんでそのシーンじゃなければいけなかったのか。本当にこれじゃなきゃいけなかったのか。自分で書いていると明確にわかるので、撮り方も自ずと決められるのですが、人の書いたホンだとそこが一番わからない。
辿ってきた道を知らないので、明確な根拠がなく、役者さんに「だからこうしてほしい」というのが伝えにくいです。
--今回は片島さんが「監督補」となっていますよね。
周防監督:通常の助監督の仕事ではなく、本当に演出を手伝って欲しいということでお願いしたんです。何かシーンをいじる時も、絶対に自分では書き直さずに、片島さんの身体を通して直してもらう、という形にしました。
僕の考えとは違う構造でできているホンに乗っかることで、いつもと違う自分の演出が出てくるかもしれない。片島さんの世界の中で僕が何をできるか?を見てみたかったんです。
中には、いくら何でも間違いだろ、っていうシーンもありましたが。
--それはどこですか?
周防監督:壁を破ってスクリーンに突撃するシーン。本気で壁に体当りしてぶち壊すと聞いて、「ああ、そういうことが許される映画にするんだ」というのが分かりました。
その映画のトーンをどのレベルで描くか、ホンを書いてる人にはわかっているわけです。だから、作品をご覧になった方だとわかると思いますが、“タンス”のシーンも、ああこういう笑いを作る映画なんだと、この映画のセンスのようなものが分かるわけです。
無声映画時代のアクション、という線で考えると「なるほどね」となるわけですが、そこを掴めていないと理解できない。
--タンスのシーン、面白かったです!逆に片島さんとして、脚本家として監督の演出に対して「嬉しい!」と感じたシーンなどはありますか?
片島氏:さすがだなと思ったのは、主人公の俊太郎(成田凌)と初恋相手の梅子(黒島結菜)が二人で活動弁士として語るシーンです。子供時代から10年後に再開して、お互いへの気持ちをそのままの言葉で言い合うんじゃなくて、活弁を通して言う。活弁の台詞が慎太郎の気持ちになる。そんなシーンにしたいなと思っていたんです。
梅子役の黒島さんが活弁の練習をそんなにしていなかったので、どうなるかなと思っていたのですが、逆に二人で気持ちを吐露するようなシーンに仕上がっていて、それがものすごくラブシーンっぽくて。
もう本当に、ありがとうございます!という感じでした。
周防監督:いや、あのシーンこそ、僕はあそこの場に立つまで、こんなに深い意味を持つシーンだとは思ってなくて、全然シナリオが読めてなかったと大反省したんですよ。現場で「どうしよう」って焦りまくって。
でも本当にドキドキしながら「うわ、こんなラブシーン撮ったことない」と思いながら、最高のラブシーンにしようと思って撮りました。
ほとんど即興演出でしたけど、実は、この映画の中で一番好きなシーンです。
片島さんにそう言って頂くと嬉しいけど、あそこが、自分でホンを書いてないということはこういうことなんだな、と痛烈に感じたシーンでもありました。
自分の好きな映画を徹底的に分析する
 (写真提供:シナリオ・センター)
(写真提供:シナリオ・センター)
--お二人に伺いたいのですが、脚本ってどのように勉強されましたか?
片島氏:僕の場合は、特に勉強したというわけではないのですが、元々頭の中で色々と想像するのが好きでした。
でも脚本を書く時はキッチリとプロットを組んだりせず、まるっきり頭から書き出しますね。設定したキャラが勝手に転がっていくのを追いかけていって、最後に考えてもいなかった着地点に着く、ということがよくあります。
--片島さんは『カツベン!』の小説も書かれていますよね。
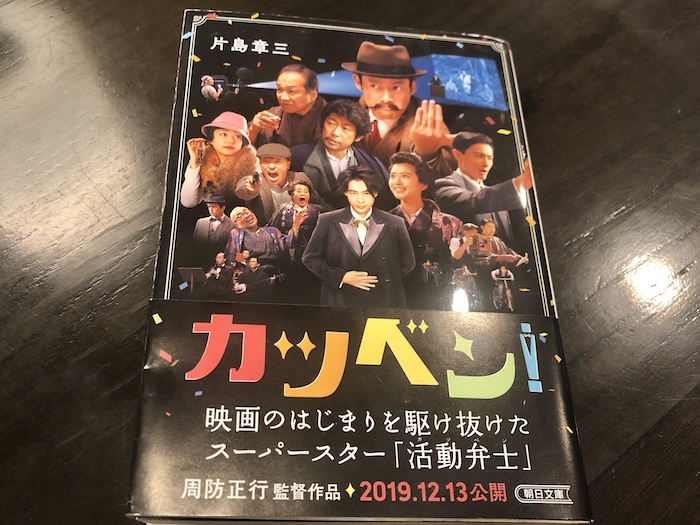 小説版『カツベン!』(朝日新聞出版)
小説版『カツベン!』(朝日新聞出版)
片島氏:小説は脚本を書いた後に取り組んだのですが、小説と脚本って、こんなに違うものなんだと感じまして、すごく大変でした。
脚本はどちらかというと、削って削って、なるべく説明するようなセリフは排除していくのですが、小説は逆で、映像がない分しっかりと説明をしていく必要がある。
ましてや大正時代の話だし、活動弁士だけではなく当時の興行のことも描かなきゃいけなくて、さらには映画が出来上がってから書き始めたので、一度終わったものをもう一回資料を引っ張り出して再構成して考えるのは、とても大変でした。
--周防さんはいかがでしょうか?
周防監督:よく言ってるのですが、シナリオの勉強に一番いいのは「自分の大好きな映画を分析し尽くすこと」です。
僕の場合、例えば小津さん(小津安二郎)のホンを何度も読み返していましたよ。なんでここから始まって、次にこういう風にしなければならなかったのか、なんてしつこく考えて分析しました。なぜ、このセリフなのか、なぜこのシーンはここで終わりにするのかとか。自分の好きな映画だったら何度でも見れるじゃないですか。そこで、徹底的に分析するんです。
その上で、今度は構成をマネて、テーマを変えて書いてみる。これはすごくいい勉強方法だと思います。
ちなみに『Shall we ダンス?』の時は、『アパートの鍵貸します』(1960年 アメリカ映画)を何度も見ています。
--ご自身で書かれているのは、なぜなんでしょうか?
周防監督:もともとは、自分が監督をやるときに「僕はこういう映画を撮りたい」という積極的に示せるものがないと、プロデューサーは何も判断できないと思ったからです。だってまだ一本の映画も作ってないんだから、どんな監督なのか全くわからない。つまり、面白いホンを書けないと、誰も「こいつに監督やらせよう」と思わないだろう、と思ったわけです。シナリオライターではなく“監督”になりたかったからこそ、そのためにはシナリオを書くしかない、と思っていたんです。
よく「周防さんって自分で書いたホンでしか作品を撮らないんですよね」と言われますが、そんなことはないんですよ。これまで何度か「こんなホンがあるんですけど撮りませんか?」と言われてきましたが、たまたま自分で撮りたいと思わなかったから断っていただけで、今回みたいに、撮りたいものがあれば撮りますよ。
 (写真提供:シナリオ・センター)
(写真提供:シナリオ・センター)
--ちなみに、周防さんは今回の脚本にどれくらい手を入れられたんですか?
周防監督:とにかく僕は、片島さんの書いてきたものを尊重しようと思っていたので、僕が手を入れてもらったのは、飲み屋のシーンで永瀬さん(永瀬正敏:山岡秋聲(しゅうせい)役)が話すところ(※)だけです。
※「説明なしでも映画はありうる。だが映画なしで説明はありえねえ -いいか、俺たちの仕事ってのはな、その程度のもんなんだ・・・」をはじめとする、山岡秋聲による活動弁士への気持ちが吐露された一連のシーン(上記セリフ部分は小説版『カツベン!』より引用抜粋)
活動弁士って、映画ファンやインテリからは嫌われていたんですよ。そういうものがあるから日本映画は発展しないんだって。全部弁士が説明したら、画で伝える必要がない。だから、映像的には何の発展もしないんだって。
でも、本当に活動弁士が日本映画にマイナスだったかというと、小津安二郎も溝口健二もその中で育っているんですよ。
小津安二郎に至っては、反面教師にしたんじゃないですかね。要するに「説明は下衆だ」って言ってた人だから、今になって思えば、活動弁士のことも指していたのかもしれません。小津さんの映画って、活動弁士を喋らせないように撮ってあるような気がします。実際、今の活動弁士さんたちは、小津さんの映画は喋りにくいって言います。
小津さんだけでなく、日本の監督は活動弁士から様々な影響を受けています。それがあってその後の日本映画の欧米とは違う独特のスタイルにつながっている面もあるんじゃないかと思います。映画ファンやインテリたちが言っていたように、活動弁士の存在が日本映画の発展を遅らせたっていうのは、あまりに一面的な見方かなって思います。
欧米の映画監督と日本とでは、全く違う制作環境だった。映画史の研究をしている人には、ぜひ「活動弁士が日本の映画監督に与えた影響」というのをテーマにしてほしいくらい、重要なことだと思います。
「表現せずにはいられない」というものを大事にするべき

トークセッションとしては以上となり、その後は会場参加者からの質疑応答を経て、小説版『カツベン!』等の販売とサイン会が行われた。
様々な質問が寄せられていたが、中でも「脚本家を目指している方へのアドバイス」への回答が素敵であった。
片島氏:オリジナルで作るとなかなか実現しないこともありますが、日本映画、もっとオリジナルが増えなきゃいけないんじゃないか、と僕は思っています。頑張りましょう!
周防監督:その世界に自分が感動できるか否か。これが大事だと思います。僕は「切実さ」って言ってるのですが、「切実」な思いがある、つまり「表現せずにはいられない」という自分の中から湧き上がってくるもの。それを大事にするべきで、それが実現するための力、面白いものを作る力になります。
会場には老若男女、様々な方が来場されており、会場となったシナリオ・センターの現役生徒さんや卒業生の方も多数いらっしゃっていた。当メディアでは最後に、シナリオ・センター卒業生であり、現在はフリーのディレクターとして活躍されている川上信也氏に、セッション後の感想を伺った。
 川上信也氏(2020年1月にアップリンク吉祥寺で公開される『川上信也短編作品集』のチラシと共に)
川上信也氏(2020年1月にアップリンク吉祥寺で公開される『川上信也短編作品集』のチラシと共に)
「小津監督といった名監督の脚本を何度も読んで分析し、その構造をもとに自分のオリジナルを生み出すというところが、大変勉強になりました。
ある意味映画って継承していくものだと思うのですが、それはただ単にコピーをするということではなくて、大げさにいうと“魂を受け継ぐもの”だと思っています。周防監督自身が名画を受け継がれてきたからこそ、長くみんなから愛される名画を生み出せる、ということにハッとしました。自分もそうやっていかなきゃなと。
また、「自分で書いたホンだからこそ、自分で全て納得できる」というお話についても、脚本は映画の設計図だと思うので、僕もまだ短編ですが5本のオリジナルを生み出してきたということで、すごく共感しました。」
ここでも、新たな名画へのバトンが受け継がれたようだ。
編集後記
周防監督による5年ぶり最新作。僕もこの公開講座の直前に、渋谷TOEIにて鑑賞してきました。
ただ一言、素晴らしかったです。
無声映画という時代において、上映小屋では観客たちが、活動弁士が語るプロットに一喜一憂し、ワイワイとリアクションしながら作品を堪能する。時には弁士に野次を飛ばすことだってある。
一人ひと席の観賞用椅子が用意され、上等な音響設備とスクリーンが整備された現在の映画鑑賞スタイルとはまた異なる、コミュニティを軸にした映画鑑賞慣習がそこには描かれていました。
「活動弁士たちの物語を描きながら、その物語自体をまるで活動写真のように撮られた作品」
そのような視点で改めて見ると、各所に散りばめられたスラップスティック・コメディの要素が盛りだくさんで、本当に音声をなくした状態でも鑑賞してみたくなる、そんな“映画愛”あふれる作品でした。
年末年始にかけて何か映画を観たいな、と思われている方。
NETFLIXやAmazonプライム・ビデオも良いですが、たまには映画館に繰り出してみて、日本映画黎明期の時代に思いを馳せてみてはいかがでしょう。
映画『カツベン!』、絶賛公開中です!
ちなみに、月刊『シナリオ』2020年1月号にて、本作のシナリオが掲載されているので、気になる方はこちらも要チェック。
本記事と併せて読むと、より理解が深まりますよ!
映画「カツベン!」
<スタッフ>
監督:周防正行
脚本・監督補:片島章三
音楽:周防義和
エンディング曲:奥田民生
<キャスト>
成田凌、黒島結菜
永瀬正敏、高良健吾、音尾琢真
徳井優、田口浩正、正名僕蔵、成河、森田甘路、酒井美紀
シャーロット・ケイト・フォックス、上白石萌音、城田優、草刈民代
山本耕史、池松壮亮、竹中直人、渡辺えり
井上真央、小日向文世、竹野内豊
映画「カツベン!」公式ウェブサイト
https://www.katsuben.jp/