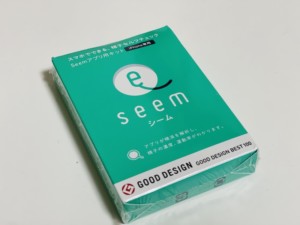愛に寄り添うテクノロジーの重要テーマの一つとして、当メディアが位置付けている妊活や不妊治療。性のヘルスケアやウェルネスの文脈で登場したテクノロジーは、どのような経緯で発展し、また現代社会におけるいちソリューションとして、どのように人々の選択肢となり得ているのか。
今回は、妊活スタートアップである株式会社ファミワンにて、公認心理師・臨床心理士・生殖心理カウンセラーとして日々ユーザーの悩みに寄り添っている戸田 さやか氏のコラムを掲載する。
※以下より寄稿文
ロマンチック・ラブ・イデオロギーとしての「性」
日本語の「性」という言葉が持つ意味は広い。性については主に1970年代までのフェミニズム研究の中で、2つの概念から述べられてきた。一つ目は、生物学的な性差を意味するセックス(sex)。二つ目は、生物学的性差の特徴をもとに、社会・文化的に意味づけられた性役割としてのジェンダー(gender)である。そして、1976年にフーコーの『性の歴史』が刊行され、三つ目の概念としてセクシュアリティ(sexuality)が注目されるようになった。フーコー以降、セクシュアリティはフェミニズムや社会学、心理学など様々な領域で“生殖、快楽、恋愛、性愛、自己表現に関わる包括的な概念”として取り上げられるものの、明確に定義されていないのが現状である。
アメリカ心理学会(2010)は、セクシュアリティの構成要素として次の4つを挙げている。
- 外性器・内性器によって規定される生物学的性(biological sex)
- 生物学的性差に基づき社会・文化的に規定された性役割や身体理解としてのジェンダー役割(gender role)
- 自分は男性である、女性である、男女という二元的区別にはあてはまらない、といった自己意識としてのジェンダー自認(gender identity)
- ある特定の性を持つ対象に情緒的・性的魅力を持続的に感じることをあらわす性的指向(sexual orientation)
特に近年では、ジェンダー自認と性的指向に多様性があることが知られ、生物学的性とジェンダー役割に縛られない多様な性のあり方が尊重されるようになってきた。
性交渉(sexual intercourse)や生殖(reproduction)としての「性」は、近代家族論のロマンチック・ラブ・イデオロギー(ideology of romantic love)という概念の中で論じられてきた経緯がある。ロマンチック・ラブ・イデオロギーとは、近代家族の特徴である恋愛結婚を支えてきた、「結婚―愛―性(性交渉)は三位一体」という思想だ。ロマンチック・ラブ・イデオロギーでは、以下の3点が前提になる。
- 結婚があるなら愛と性がある
- 愛があるなら性と結婚がある
- 性があるなら愛と結婚がある
この思想においては、「セックスレスは病理」、「不倫・浮気や婚外性交渉はタブー」とされている。また、性は生殖のための行為という意味も含んでおり、結婚―愛―性の結果として子どもを授かるのが自然という社会通念が醸成された。近年では、事実婚、同性婚、性交渉を経ない妊娠(不妊治療)、結婚・出産・育児を前提としない人生を選ぶ人も珍しくない。また、互いの婚外性交渉を認めているカップルや、全く性交渉をしないカップルもいる。従来の夫婦や家族という概念そのものが変容しつつあると言えるだろう。
多様な性を認めるリプロダクティブヘルス・ライツの思想
これに対して、性というテーマの転換点となったのは、1994年にエジプトのカイロで開催された国際人口開発会議(International Conference on Population and Development : ICPD)である。ICPDでリプロダクティブヘルス・ライツ(Reproductive health and Rights:性と生殖に関する健康と権利)の保証が宣言され、多様な性のあり方や、性と生殖の健康・権利を重視する流れが世界的なムーブメントとなった。日本にもこの影響は大きく、これまで声をあげられなかった当事者たちが様々な形で自己表現するとともに、学術的にもリプロダクティブヘルス・ライツの視点が取り入れられるようになった。
セックス・セラピー(Sex therapy)という言葉をご存知だろうか。セックス・セラピーは、「性に関する悩み、性機能不全、性障害の存在を認識し、それらに取り組み、治療する」(モントリオール宣言、2005)ことを一つの目的としている。セックス・セラピーが中心的に扱う問題は、性機能不全、性別への違和感、非典型的な性的関心(パラフィリア;Paraphilia)などによる、性行動およびセクシュアリティ、社会生活にまつわる困難である。勃起、射精、オルガズムなど性機能の悩みに対して、セックス・セラピーでは該当する診療科(泌尿器科や婦人科)の医学的治療と併用するのが基本だ。
セックス・セラピーはこれらの「病理」に対する治療のひとつであるとともに、リプロダクティブヘルス・ライツを向上させる一つの方法でもある。がん治療などで乳房を取る、人工肛門になるといった身体の変化によって性交渉に強い不安を感じている場合や、身体障害のため性機能の問題はあるが性交渉を楽しみたいといった、身体と性の健康に関する問題を扱うことも少なくない。
不妊治療というテクノロジーが孕むギャップの正体
個人や家族のライフサイクルに関する理論では、人はパートナーと出会い、子どもを授かり育てることが前提とされてきた。例えば、Carter & McGoldrick(1989)は家族の発達を、以下の6つの段階に分けて論じている。
- 親元を離れて独立している未婚の若い成人の時期
- 新婚の夫婦の時期
- 幼児を育てる時期
- 青年期の子どもをもつ家族の時期
- 子どもの出立と移行が起こる時期
- 老年期の家族
新婚の夫婦の時期以降は子どもがいることを前提とした家族発達が論じられていることからわかるように、不妊は家族にとって発達的危機と考えられてきたのである。先に述べたロマンチック・ラブ・イデオロギーの思想が強く影響していることは言うまでもないだろう。
そこにまた一つ大きな変革を与えるのが、医療というテクノロジーを用いた不妊治療である。不妊治療の登場は性交渉を介さない妊娠を可能にし、「結婚―愛―性(性交渉)は三位一体」というロマンチック・ラブ・イデオロギーを崩すことになる。しかし、我々の中に刷り込まれたロマンチック・ラブ・イデオロギーの思想は根強く、それが「子どものいない人生」や「治療を受けて子を授かること」への抵抗感に繋がっていると言えるだろう。不妊治療はその名称から、「何か医学的な原因(問題)があって妊娠できない場合、医学の力でその原因を解決して妊娠させるもの」というイメージを彷彿とさせる。だが実際には、明らかな医学的原因が発見できない不妊が約50%を占め、様々な薬や治療法を組み合わせながら試行錯誤するのが不妊治療である。つまり、不妊治療にできるのは、精子や卵子、子宮が元々持っている自然に妊娠する力を、検査・薬・施術によって“補助”することだけなのだ。ここに、不妊“治療”というテクノロジーがもつイメージと実態の、乖離があると思われる。
「Not for me」から「Yes!For me」に向けた性教育へ
性のヘルスケアやウェルネスの文脈で登場したテクノロジーの方が、不妊治療に比べれば利用する当事者にとってハードルが低いかもしれない。性の健康課題をテクノロジーで解決できる商品(製品)やサービスのことをFemTech(フェムテック)やMenTech(メンテック)といい、特に前者は2020年10月、自民党にフェムテック振興議員連盟が立ち上がったことでも注目を集めている。
フェムテックやメンテックはヘルスケアやセクシュアル・ウェルネスの文脈で登場しているため、ユーザーが自ら望んで主体的にプロダクトやサービスに接近する。主体的にサービスを選ぶことができるし、「Not for me(私向きではない)」と感じれば手放すことができる。ここが、不妊治療というテクノロジーとの大きな違いだろう。
不妊治療に臨むカップルの多くは、そもそも自分たちに不妊治療は必要ないと考えていたところに、不妊という現実を突きつけられて初めて治療にたどり着く。この「Not for me」が「Yes!For me(私のためのものだ)」と感じられるようになる鍵は、若年期からの性教育にある。誰もが必ずしも不妊治療を受ける必要はないが、必要な人にとって心理的ハードルが低く、アクセスしやすい治療になることが必要なのだろう。
その時には、ロマンチック・ラブ・イデオロギーという思想が古のものとして語られるようになっているかもしれない。
(文・戸田 さやか)