2021年11月11日 〜12日にかけて開催された、世界最大級のFinTechイベント『World FinTech Festival Japan 2021』(以下、WFFJ2021)。「金融インターオペラビリティとAPIエコノミーの復建」というテーマで設置されたセッションでは、決済サービスやインフラ、および標準規格の策定等に携わる有識者が集まって、APIとインターオペラビリティの議題のこれまでと現在地点、そしてこれからのあり方について、それぞれの意見を寄せ合った。
後編となる本記事でも引き続き、同セッションの様子をお伝えする。

- 富士榮 尚寛(一般社団法人OpenIDファウンデーション・ジャパン 代表理事)
- 川越 洋(株式会社ことら 代表取締役社長)
- 丸山 弘毅(株式会社インフキュリオン 代表取締役社長)
- 三輪 純平(リクルート プロダクト統括本部 シニアエキスパート)※モデレーター
事例づくり、他業界への広がり、複数APIの活用が重要

三輪:2017年に全銀協から公表された「オープンAPIのあり方に関する検討会報告書」の中で、4つの大きな原則(※)が掲げられました。当時としてはかなり革新的な内容だったと思うのですが、まずはこれについてのお考えを教えてください。
※【原則1】API利用者目線を意識した分かりやすくシンプルな設計・記述とすること、【原則2】APIの種類に応じた適切なセキュリティレベルを確保すること、【原則3】デファクトスタンダードや諸外国のAPI標準、国際標準規格との整合性を意識すること、【原則4】仕様変更によるAPI利用者への影響をコントロールすること
丸山:ヨーロッパの動きを見ながら、日本もより金融イノベーションを進めるという観点で、4原則は非常に優れたものだったと思います。日本の金融はプリンシプルベースでありながら、かなり事細かに決めてフォーマットを決めるものも多いのですが、APIはまさにオープンイノベーションの概念でプリンシプルベースであると言えます。あとはそれをベースにどんどんと発展させていくというものが持ち込まれたので、フィンテックと金融業界の橋渡しとしては非常に素晴らしいものができたなと思っています。
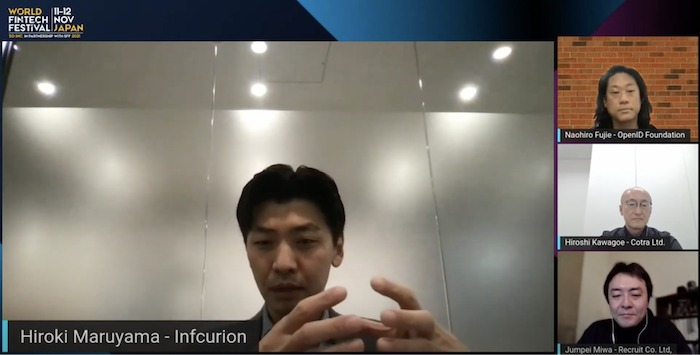
丸山:一方でこれをもとに日本の金融機関のAPIがどこまで発展しているかというと、残念ながらすでに見えている課題の範囲でのAPI活用に留まっていると感じます。また、あの報告書ではカード決済や証券といった他の金融機関も色々と参考にすべきと明記されているのですが、これがなかなか広がらなかったところもあると思っています。
今はどちらかというと銀行対フィンテックという側面が強いのですが、これをもっと幅広く、APIがあってそれを共通的に使って行くという「事例」をなしていくのが重要かなと思います。
まとめると、事例づくりと他業界への広がり、それから複数のAPIを使うというところをもっと進めていくのが、今後重要なことだと思います。
三輪:まさにそこが重要な論点なんですよね。私も金融庁時代は、銀行とフィンテック企業をどうしても繋げたいというのがありましたが、一方でそこがつながっているだけの世界でしかなくて、他の広がりみたいなところは、確かになかったなと。オーストラリアみたいな国は他業界への広がりを議論していたところがあるので、これからはそういう視点も含めながら進めていくのが、まさにインターオペラビリティの話にもつながっていくのかなと感じます。
日本からもコントリビューションを積極的にやっていくべき
三輪:この検討会報告書の原則3で「デファクトスタンダードや諸外国のAPI標準、国際標準規格との整合性を意識する」と記載されていまして、まさにFAPIがそれに近い考え方だと思います。APIの観点でOpenIDの活動と相互運用性を高める動きがある中で、国際標準の動向は今後どういう形で機能していくのでしょうか。
富士榮:標準化って、技術の側面からだけで進むものでもないと思っています。もちろん技術の側面だと、例えばFAPIに関していうとサーティフィケーション・プログラムというものを作っていまして、事業者等が公開するAPIがちゃんと準拠できているかの検証をするようなテストプログラムみたいなものは提供しています。ですので、それにパスさえすればつながるはずだよねという、仕掛けとしては用意しています。
ただそれだけで本当にみんなが使うようになるかというと、それはまた話が違うわけです。例えば先ほどの丸山さんのお話だと、日本の場合は事例が必要だよねと。もっと言うと、標準というのは欧米で作られたものを使うのか、それとも作りに行くのか。この観点が一番重要かなと思います。
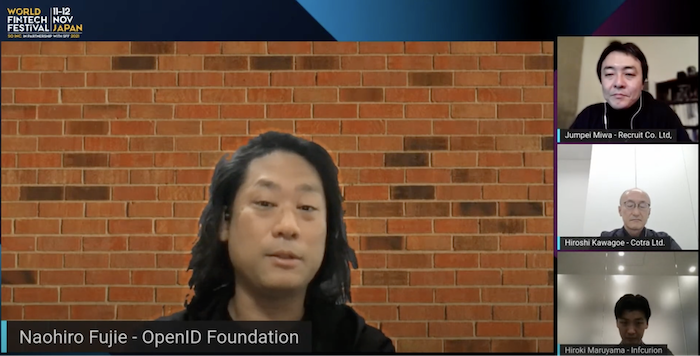
富士榮:FAPIもOpenID Connect for Assuranceも、標準化の作業としては、実際に事業をやっている方々がユースケースを持ち寄ってきて、そこから標準とは何かを決めていくプロセスとなります。残念ながら日本の企業は、言語バリアもあってか、そこに入ってこれていないという事情があるわけです。
もしもそこが進んで、日本の事情に即して標準化されたものが出てくれば、先ほどのエッジ部分のシナリオだけではなくて、もっと根幹に近いようなシナリオも、より標準との整合性が高まると思います。
あとは標準化自体も、実際の実装された事例を何個か作って初めて「やっぱり標準として使えるよね」という作業をやったりもするので、そういうパイロットプログラムを日本でも動かせるようになるんじゃないかなと。よって、今後の国際標準との整合をとる上で、日本からもコントリビューション(貢献)を積極的にやっていくことが重要だと思っています。
三輪:まさに事例作りが重要なファクターですよね。私からすると、もうちょっと企業が自発的に考えて、国際標準に盲目的に準拠するのではなくて、ツールとしての役割とその活用方法をもう少し合わせて考えていくと、より良い世界ができてくるかなと思いました。
川越:すごく重なる経験があるので少しお伝えしますと、かつてLEI(Legal Entity Identifier:取引主体識別子)を作るときに財団(グローバルLEI財団)が設立されたのですが、その立ち上げメンバーに私も入っていました。その時に、国際標準化の取り組みに対する欧米と日本のスタンスの違いを強く感じました。
一番の違いは踏み込み具合です。標準を作っていくということは、非常に多くのステークホルダーに対して1つのコンセンサスをとっていかねばならないので、ものすごく時間と労力がかかる作業です。これそのものは収益を生まないので、なかなか日本企業はここに労力を割かないのが実態です。一方で欧米企業の中には、積極的にリソースを投入するところがあるわけでして、なぜかというと、標準化をベースにビジネスを立ち上げていくと、立ち上げた後に非常に大きなスケールが待っていることをちゃんと理解しているからだと感じました。
そういう意味でも、日本ではそういうカルチャー・ビヘイビアから変えていかないと、なかなか変わらないかなと強く感じました。
ことら設立の目的は、まさにインターオペラビリティにあり

三輪:金融庁がこの夏に「2021事務年度金融行政方針」を出しまして、インターオペラビリティの観点で「ことら」が語られていると思うのですが、それについてどう思われていますか?また今後の運営方針についても伺いたいです。
川越:「ことら」は、キャッシュレスを推進する過程で分断してしまった我が国の決済シーンをつなぎ合わせということを目指しています。なので、まさにインターオペラビリティが設立の目的であります。
一つ申し上げると、政府や当局から言われてやったということでは決してなくて、銀行が自主的に始めた非常に良いタイミングで、政府サイドからもサポートいただいたというのが実態です。そういう意味では、送金サービスはスケールが大事なので、引き続きパブリックセクターからの強いご支援があればと思っています。
非常にステークホルダーが多く、調整に手間も時間もかかるのは日々実感していますが、これについては近道はないとも思っています。強いて言えば、コミュニケーションを大切にすることかなと。目指しているビジョンをステークホルダーとしっかりと共有することで、協力者が自ずと増えてきます。
今はまだほふく前進といったところですが、個人的には楽観的に捉えて楽しく取り組んでいます。
三輪:各ステークホルダーが今後どうやって動いていったら良いかは、かなり重要ですね。それでは最後に、トラストが生まれるような形でインターオペラビリティを高めるにはどうしたら良いか、それぞれお一人ずつアドバイスをお願いします。

丸山:ある種コンフリクトがある人たちが集まって標準化やAPIの話をしていると思うのですが、捉えるべきは「どういう社会になるべきか」だと思います。自社のビジネスでこうなっているというのではなく、最終ゴールを意識しながらコントリビュートする姿勢でもって社会を発展させる意識を持つ。そのためにトラストをみんなで共有することが大切だと思います。
富士榮:まさにその通りだなと。自社のことだけを考えていてはいけないというのは、個社もそうだし業界もそうでしょう。
例えば金融で言うと犯収法(犯罪収益移転防止法)という枠組みの中での話で、かたや携帯電話事業者なら携帯電話不正利用防止法の枠組みの中での話で、それぞれKYCをやります。
でも中身を見ると、やっていることはそれほど変わらないよねと。そういうトラストフレームワークを超えた「信頼」というものを、相互運用を一つのキーにして、どうドライブできるか。この辺の課題感はグローバルでも一致していて、最近ではGAIN(※)と呼ばれる取り組みも発展してきています。日本もうまくこういうのに参加していくことで、より良い社会が出来上がるんじゃないかなと思っているので、推進していきたいと思います。
※GAIN:Global Assured Identity Networkの略で、責任ある参加者のみで構成されるインターネット上のオーバーレイネットワークのこと。詳細はこちらを参照
川越:ことらは黒子の存在ではありますが、一つだけ忘れてはいけないのが、エンドユーザーの視点かなと思っています。
World Fintech Festival Japan 2021レポートシリーズ by LoveTech Media
Report1. Web3.0に向けて、Stake Technologies渡辺氏が”日本人として”目指すこと
[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20211112_wffj2021_1/”]Report2-前編. BaaS、ことら、OIDC4IDA等。有識者が語るAPIエコノミーの現在地
[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20211116_wffj2021_2_1/”]Report2-後編. APIエコノミーで問われる「標準」との付き合い方とは
[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20211117_wffj2021_2_2/”]Report3. 金融包摂(Financial Inclusion)の観点で考える、APIの未来
[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20211119_wffj2021_3/”]Report4. Trusted Webタスクフォースメンバーが語る、新たな「トラスト」の仕組み
[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20211122_wffj2021_4/”]Report5. 急成長する東南アジア市場。現法責任者らが考える地域の魅力談義
[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20211124_wffj2021_5/”]Report6. シンガポール政府Chief Fintech Officerと考える、日本の強みと課題
[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20211126_wffj2021_6/”]













