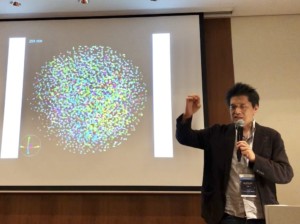LoveTech Media編集部コメント
ヘルステック分野のリーディングカンパニーであるフィリップス・ジャパンが掲げる「Heart safe city」構想が本格始動した。
「Heart safe city」構想とは、心肺停止後の社会復帰率を向上させるプログラムである。
平成30年版総務省消防庁救急救助の現況によると、日本における年間心肺停止件数は約12万件で、そのうち心原性の件数が約7万件である。それに対して設置されているのが、こちら、自動体外式除細動器(Automated External Defibrillator、以下AED)である。いわゆる電気ショックによって心臓の拍動を正常化させるための医療機器のことだ。

写真引用:フィリップス・ジャパンのホームページ
このAED、日本は世界一の普及率といわれており、医療機関や消防機関を除く公共の場所には全国で合計50万〜60万台のAEDが設置されているが、心肺停止後のAED使用率は異常に低い。
目撃のあるものが約2万5千件で、AEDが使用された件数は1200件程度で約4.9%となっている。
AED使用率の向上は、AEDの適正配置に加え、その場に居合わせる人々がAEDの操作方法を理解するとともに、救命のために一歩を踏み出せるかどうかにかかっている。
そこでフィリップスでは、AEDの適正配置、ファーストレスポンダー(救急隊に引き継ぐまで適切に応急手当が出来る救護者)の育成サポート、行政や自治体との体制づくりを推進し、日本の社会復帰率「世界一」を目指すというHeart safe city構想を掲げた。
そして今回の本格始動に併せ、IoT技術とアプリの連動により、より広範囲において、必要な人への一斉通知が可能な仕組みを構築する。

これにより、人がたくさん集まるような大規模イベントの救護体制をはじめ、各組織における自助・共助を強化した体制作りが可能になる。
AED自体を見たことのある方は非常に多いと思うが、その使い方に自信のある方はどれくらいいるだろうか。
倒れた方に、誰かが気がつき、然るべきひとがAEDを持ってきて、AEDを使用し、蘇生する。
こういった救命の連鎖を強固にするため、今回のSOSボタンの存在に期待し、また同社によるファーストレスポンダー育成活動に期待したい。
以下、リリース内容となります。
リリース概要
株式会社フィリップス・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役社長:堤 浩幸、以下 フィリップス)は「2030年までに30億の人々の生活を向上させる」をビジョンに掲げ、健康な生活、予防、診断、治療、ホームケアにいたるヘルスケア・プロセスのすべてにイニシアティブを持ち「もっと健やかな未来へ」をコンセプトとして、すべての人の健康に貢献していきたいと努めております。
このたびフィリップスは、2018年9月18日に発表した「Heart safe city」の構想について、本格始動をいたしましたことをご報告いたします。Heart safe cityではAEDの適正配置、ファーストレスポンダー(救急隊に引き継ぐまで適切に応急手当が出来る救護者)の育成サポート、行政や自治体との体制づくりを推進し、日本の社会復帰率「世界一」を目指します。
日本における心肺停止からの社会復帰率は著しく低く、世界の最善事例であるシアトルやコペンハーゲンと比較すると大きな差があります。これはAEDの適正配置に加え、その場に居合わせる人々がAEDの操作方法を理解するとともに、救命のために一歩を踏み出せるかどうかにかかっています。
そこで、フィリップスではHeart safe cityが本格始動するにあたり、IoT技術とアプリの連動により、より広範囲において、必要な人への一斉通知が可能となります。これにより、人がたくさん集まるような大規模イベントの救護体制をはじめ、各組織における自助・共助を強化した体制作りが可能になります。

SOSボタン(近日発売予定) / 無料スマートフォンアプリ 「MySOS」と連動
特長
- LTE-M通信規格
- SOSボタン設置が容易
- 救援者への通知設定範囲が可能ボタン押下より10秒強で一斉通知可能
- ボタン押下より10秒強で一斉通知可能
Heart safe cityとは

1. AEDの適正配置
AEDの適正配置については、令和元年5月17日付けで厚生労働省医政局長から各都道府県知事等あて通知されているようにその重要性は日々高まっています。フィリップスは、AEDの適正配置に関するガイドライン補訂版(H30.12.25)を根拠にし、施設に合わせた提案をおこなっています。いざという時に、使用できるAEDを目指しています。
2. ファーストレスポンダーの育成サポート
地域の消防組織や日本赤十字社などが行う講習会の補完的な講習会の位置づけと考えています。例えば、消防組織で普通救命講習を受講した場合、3年間の有効期限となります。その3年間継続的にスキルや意識を保つことを目的としています。自助、共助を強化するためには、そういった継続性が欠かせません。また、時間がないという人にも簡易に学べる場を設けられる学習方法をフィリップスはサポートします。
3. 行政や自治体との体制づくり
Heart safe city運用にあたり個人情報の問題や地域住民への参加において行政や自治体からの協力なしでは実現不可能です。根本となるものは、地域にいる人とのつながりであり、そのつながりが自助・共助を生み出します。様々な組織がそれぞれの役割を担いながら、新しいまちの価値として認識し、協働することが必要不可欠となります。
現状の数値的課題とSOSボタンによる期待値
平成30年版総務省消防庁救急救助の現況よれば、年間日本における心肺停止件数は、約12万件で、心原性の件数が約7万件であります。そのなかで目撃のあるものが約2万5千件でAEDが使用された件数は1200件程度で約4.9%となっています。現在、日本には、50~60万台あるAED(他社含む)といわれており、使用率は年々あがっていますが、まだまだ改善の余地はあります。
AEDは、医療機器として一般人にも使用が認められています。そして、AEDの蘇生事例が起こると、メディアなどでは“奇跡”と称せられます。その理由は、大きく3つあると考えています。まず、倒れた方に、誰かが気がつき、然るべきひとがAEDを持ってきて、AEDを使用し、蘇生した。こういった救命の連鎖を強固にするためには、このSOSボタンの存在はかかせません。いままで難しいとされてきた早期通報と初動のレスポンタイム短縮を可能にします。
フィリップスについて
1891年オランダで創業し、ビジネスモデル変革と長い歴史の中で培った技術と知見を生かしながら、健康な生活、予防、診断、治療、ホームケアという「一連のヘルスケアプロセス」においてイノベーションを実現してきたヘルスケア・カンパニーです。フィリップス・ジャパン(旧フィリップス エレクトロニクス ジャパン)は、超高齢者社会を迎える日本の健康と医療の問題に貢献したいと、2019年4月1日よりフィリップス・レスピロニクス合同会社と統合し、ヘルステックカンパニーとして、ヘルスケア分野の変革に取り組んでいます。今後、「病院」というプロフェッショナルな分野におけるフィリップスの先進医療機器と、パーソナルヘルスと呼ばれるオーラルヘルスケア(電動歯ブラシ)、AED、在宅呼吸器などがクラウド上で繋がり、デジタルプラットフォーム上でビッグデータが解析されることで、総合的な医療、リアルタイム分析、付加価値サービスが可能になります。これにより、人々の健康な生活、予防、診断、治療、ホームケアという「一連のヘルスケアプロセス」において、革新的な医療ソリューションを提供し、医療従事者の皆様、患者様だけでなく、すべての人々の健康な生活への貢献を目指しています。(https://www.philips.co.jp)
ロイヤル フィリップスについて
ロイヤル フィリップス(NYSE:PHG, AEX:PHI)は、人々の健康の向上にテクノロジーで貢献するヘルステック分野のリーディングカンパニーです。健康な生活、予防、診断、治療、ホームケアという一連のヘルスケアプロセスを通じて、先進的なテクノロジーと、医療従事者および消費者のインサイトを基に、人々の健康を改善し良好な結果をもたらすための包括的なソリューションを提供しています。主な事業領域は、画像診断、画像誘導治療、生体情報モニター、ヘルスインフォマティックスのみならず、パーソナルヘルスや在宅医療まで、さまざまな領域に渡ります。フィリップス ヘルステック事業の2018年の売上高は181億ユーロ、オランダを拠点に全世界に77,000人の従業員を擁し、世界100ヵ国以上でビジネスを展開しています。フィリップスに関するニュースはこちらからご覧ください。(http://www.philips.com/newscenter/)